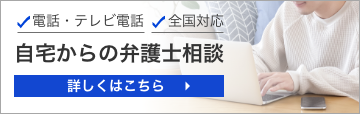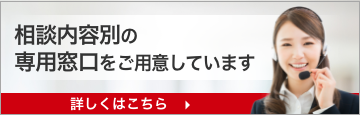「特許」と「実用新案」の違いを解説
- 商標・特許・知的財産
- 特許
- 実用新案
- 違い

令和元年の統計によれば、広島県では2315件の特許出願があり、77件の実用新案の出願がありました。
せっかく製品やサービスを新たに発明しても、適切に特許や実用新案を申請して登録されなければ、その発明や考案は法的には保護されません。
「自分の発明を特許として申請するべきか、実用新案として申請するべきか」という点について悩まれる方もいるでしょう。また、審査の結果として認められた特許や実用新案が第三者に侵害されてしまった場合にどのように対応すればいいのかについても、不安を抱かれる方がおられます。
本コラムでは、特許と実用新案の違いや出願と審査の手続き、権利行使の方法などについて、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスの弁護士が解説いたします。
1、特許と実用新案の違い
特許と実用新案は似ているようで大きく違う制度です。
まず、特許と実用新案の違いについて解説します。
-
(1)特許とは
特許とは、「発明」を保護するための制度(特許法第1条)です。
また、「特許権」とは発明を独占的に実施(発明の使用や譲渡など)することのできる権利です。
特許と実用新案の違いは、特許の対象は「発明」である、という点にあります。
特許法では「発明」を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいうと定義しています(特許法第2条第1項)。
このうち、「高度のもの」であることを要件として定義している部分が、特許と実用新案の違いのポイントとなります。 -
(2)実用新案とは
実用新案は、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」を保護する制度(実用新案法第1条)です。
特許は「発明」を保護する制度であるのに、対して実用新案は「考案」が保護の対象になります。
実用新案法では「考案」を「自然法則を利用した技術的思想の創作」をいうと定義しています(実用新案法第2条第1項)。
「発明」も「考案」も「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるところは同一ですが、「考案」の定義には「発明」と違い、「高度なもの」という要件がありません。
したがって、実用新案においては創作について発明ほどの高度性は要求されないために、技術的には簡易な創作物も対象に含まれることになります。
もっとも、実用新案は保護の対象を物品の形状、構造又は組合せに係る考案に限定しているため、特許では保護されている「方法」に関する創作については対象にされていません。 -
(3)特許と実用新案の違い
そのほかの特許と実用新案の違いとしては、「審査手続」「侵害への対応(権利行使)」「存続期間」があげられます。
① 審査手続
特許の審査では、概要や書類などの不備をチェックする「方式審査」をクリアすると、その次に、「発明の内容が特許を与えるにあたってふさわしいのか」「特許が認められる要件を備えている発明なのか」を審査する実体審査が行われます。
つまり、特許権が認められるためには、方式審査と実体審査の両方を通過する必要があるのです。
一方で、実用新案は、登録時に実体審査は実施されず、方式審査と基礎的な要件審査のみとなっています。実用新案では実体審査がされるのは、「実用新案技術評価請求」という手続きを行った場合のみです。
このように、「特許としてふさわしいのか」という実体の内容まで踏み込んで審査される特許と、方式審査のみの実用新案では、登録の難易度に大きな差があるのです。
② 侵害への対応(権利行使)
特許権が侵害されていることが判明した場合、権利者は直ちに特許権に基づいて侵害行為の差し止めを請求したり、損害賠償請求を行ったりすることができます。
一方で、実用新案権の場合には、仮に登録した実用新案が他の者に無断で利用されていたとしても、直ちには差し止めなどの権利行使をすることができません。
「実用新案技術評価請求」という手続きを行い、審査官が一部の登録要件を判断して認められた場合に出される「技術評価請求書」を提示して警告してからでなくては、権利行使ができないことになっているのです(実用新案法29条の2)。
実用新案の審査では、実用新案にふさわしい考案なのかについて実体審査がされていないことが理由です。
③ 存続期間
原則として、特許権の存続期間は、「出願の日から20年」(特許法第67条第1項)です。
一方で、実用新案権の存続期間は、「出願の日から10年」(実用新案法15条)となります。
2、出願に必要なものと審査の流れ
以下では、特許と実用新案の出願に必要となるものと、審査の流れについて解説します。
-
(1)特許の場合
特許法の審査は書面主義になっており、特許を受けようとする発明は文書によって特定されます。
特許出願の願書には、「特許請求の範囲」「明細書」「必要な図面」「要約書」を添付して出願します(特許法第36条第2項)。
「願書」には発明者や出願人の氏名などを記載します。
「特許請求の範囲」は出願人が保護を求めたい発明の範囲を記載するものであり、特許権が与えられる対象を定める重要な書類です。
「明細書」や「必要な図面」は、発明の内容をより詳細に説明するための書類です。
特許の出願がされると、特許庁で審査が開始されて、特許が認められるかどうかの判断がされることになります。
先述した通り、特許の審査には「方式審査」と「実体審査」の2段階が存在します。
方式審査は形式面で不備がないかを審査するものであり、出願されると自動的に行われます。
出願書類の記載事項や添付書類の不備がないかといったことが審査されます。
このような形式的な要件に不備があった場合には、補正が命じられることになるのです
実体審査は、「その発明の内容が特許を与えるにあたってふさわしい内容なのか」「特許が認められる要件を備えている発明なのか」を審査するもためのものです。
実体審査が実施されるためには、「出願審査請求」という請求を行う必要があります(特許法第48条の2)。
出願審査請求は、出願人のみならず、ほかの誰でも請求することが可能です。
また、出願審査請求の期限は、出願日から3年間です。3年を経過しても出願審査請求がない場合には、出願は取り下げとなります(特許法第48条の3第4項)。
これらの審査において、「特許の要件を備えている」と判断された場合には、特許が認められる「特許査定」がなされます(特許法第51条)。
その後の特許料納付などの手続きを経て、特許権が発生することになるのです。
なお、出願審査請求をしてから、最終的な処分(特許査定や拒絶査定など)が出るまでの審査期間は、令和3年度では15.2カ月となっています。 -
(2)実用新案の場合
特許と同様に、実用新案も、書面によって審査されます。
出願に際しては、願書に「実用新案登録請求の範囲」「図面」「明細書」「要約書」を添付して出願します(実用新案法第5条第2項)。
また、実用新案では保護対象が物品の形状、構造又は組合せに係る考案に限定されているために、必ず図面を提出しなければなりません。
実用新案の出願がされると、特許庁で審査が開始されます。
ここでは方式審査と基礎的要件審査のみが実施され、問題がないと判断されたら、実用新案が登録されることになります。
実用新案における方式審査では特許の場合と同様に書類の不備などが確認されるほか、公序良俗に反しないかなどの基礎的な要件審査も行われます。
通常は、書類に不備がなければ、出願から平均2~3カ月ほどで実用新案の登録が認められることになります。
実体の審査が開始されるのは、「実用新案技術評価請求」を行った場合のみです。
実用新案技術評価請求による実体審査では、出願または登録された考案について、実体的な要件である「実用新案としてふさわしいのか」などの新規性などの要件該当性の評価を審査官に求めるものです。
3、切れた特許や実用新案はどうなる?
特許権の期限は、出願の日から20年間です。また、実用新案権の期限は、出願の日から10年間です。
特許権や実用新案権の期限が過ぎた場合には、その権利が失われて、誰でも自由に実施することができるようになります。
なお、特許権や実用新案権を有している間はその製品に「特許を取得している」などといった表記をされていることがよく見られますが、期限を過ぎた後にもそのような表示をすることは「虚偽表示」として禁止されています(特許法第188条、実用新案法第52条)。
これに違反した場合には刑事罰の対象になるおそれがあることに注意してください(特許法第198条、実用新案法第58条)。
4、企業で発明した利益を守るなら弁護士に相談を
特許権と実用新案権とでは、保護の対象、審査手続、保護される期間、権利行使の方法などが異なっております。
せっかく時間とコストをかけて開発したものであっても、しかるべき権利を保護しなければ、元も子もありません。
この分野に詳しい弁護士であれば、特許として申請すべきか実用新案にするべきか、審査手続への対応などについて、法律の専門家としてアドバイスをすることができます。
また、特許権や実用新案権が侵害されていることが判明した場合に行う差し止めや損害賠償請求についても、訴訟の専門家である弁護士がサポートできます。
特許についてお悩みの方は、弁理士だけでなく弁護士にも相談することを検討してください。
5、まとめ
特許として申請するか、または実用新案にするかについては、発明や考案の内容について十分に検討したうえで適切に選択する必要があります。
また、とりわけ特許については、その審査手続は複雑になっております。そして、権利侵害があれば、差し止めや損害賠償請求訴訟を提起する必要があるのです。
ベリーベスト法律事務所では、知的財産権に関する知見を有する弁理士が多数所属する特許業務法人ベリーベスト国際特許事務所と連携しながら、特許や実用新案に関する各種の手続きについてワンストップで対応しております。
特許や実用新案の出願を検討されている方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|