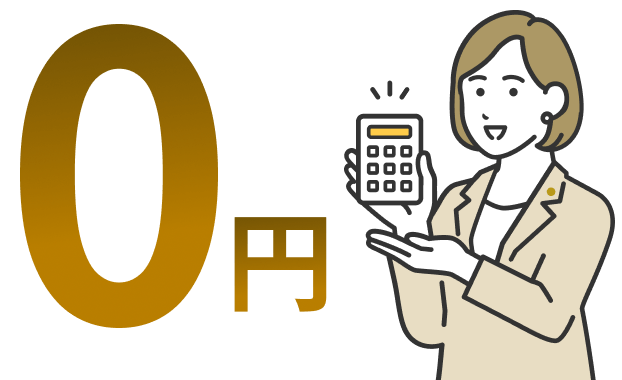遺産分割協議の特別代理人:役割から選任方法、注意点を解説
- 遺産分割
- 遺産分割
- 特別代理人

遺産相続では、未成年の子どもが相続人になることがあります。
しかし、親も相続人であるときには、親と子は「相手が遺産を少なく相続すれば、自分が多く相続できる」というお互いの利益が対立する関係となるのです。
このようなケースでは、子どもの「特別代理人」を選任したうえで遺産分割協議を行わなければならないとされています。
たとえば、令和元年度には、広島家庭裁判所に179件の特別代理人の選任の申し立てがなされているのです。
未成年者が相続人になる遺産相続では、特別代理人の制度について理解しておくことが重要になります。
本コラムでは、「遺産分割における特別代理人」の役割や選任方法、注意点について、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスの弁護士が解説いたします。
1、特別代理人の役割とは
-
(1)特別代理人の役割
「特別代理人」とは、親権者と未成年者の利益が相反するときに、親権者に代わって未成年者の代理人として法律行為などを行う人のことを指します。
特別代理人は、未成年者の子どもの利益を守る役割を担う存在です。
特別代理人なるためには、家庭裁判所で選任が認められることが条件となります。一方で、資格などは特に必要とされません。
一般的に、未成年者には、大人と比較すると能力や経験などが十分に備わっていません。そのため、法律上、未成年は「保護されるべき存在」と見なされているのです。
通常であれば親権者(または後見人)が未成年者の法定代理人なり、法律行為や財産管理を代理して行うことができます。
しかし、未成年者と親権者などの利益が相反する場合には、親権者は代理人としての資格を失います。親権者が自身の利益を優先することが未成年者の不利益につながる、という関係にあるためです。
このようなケースでは、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てて、未成年者の代理人を定める必要があるのです。
なお、遺産分割以外の場面でも、たとえば債務者である親が子どもの財産に抵当権を設定する場合や、子どものみが相続放棄する場合などには、「特別代理人」の選任が必要とされます。 -
(2)特別代理人の選任なく行われた遺産分割の効果
親権者と未成年者の利益が相反する状況において、特別代理人の選任なく親が子どもを代理して遺産分割が行うことを「無権代理行為」と言います。
無権代理行為に対しては、遺産分割の「無効」を主張することができます。
そのため、子どもが成人したのちに「無効」を主張されてしまうおそれがあるのです。
2、遺産分割で「特別代理人」の選任が必要となる場合
-
(1)親権者と子どもの両方が共同相続人であるとき
先述したように、親権者と子どもの両方が共同相続人であるときには、お互いに利益が相反する関係にあります。
そのような場合に遺産分割協議を行うためには、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があるのです。
たとえば、Aさんが亡くなり、法定相続人は配偶者Bさんと、AB間の未成年の子どものCさんの二人であったとします。
このようなケースでは、Aさんの相続について親権者であるBさんと未成年者Cさんは「どちらか一方が相続財産を多くもらえば、他方は少なくなる」という利益相反の関係にあたります。
そのため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て、Cさんの特別代理人とBさんとで遺産分割協議を行わなければなりません。
一方、子どもの親権者であっても、親権者自身が相続人でないときには特別代理人の選任は必要とされません。
たとえば被相続人に認知されている子どもがいたときには、子どもは相続人になりますが、被相続人と婚姻していない子どもの母は相続人にはなりません。
このような場合では特別代理人の選任は必要なく、母が子どもを代理してその他の共同相続人と遺産分割協議を行うことができるのです。 -
(2)一人の親権者につき複数の未成年者がいるとき
一人の親権者について複数の未成年者がいるときにも、特別代理人の選任が必要となります。
たとえば、被相続人には、離婚した元妻Xが親権をもつ二人の未成年の子ども(Y、Z)がいたとします。
この場合、子どもYとZは被相続人の相続人になります。
しかし、元妻Xは相続人にはなりません。
このような場合では、YとZの親権者はXなので、XはYまたはZの一方の代理人になることは可能です。
しかし、XがYとZの双方の代理人になることはできません。
これは、利益の対立するYとZの代理人になってしまうと、双方または一方の利益を損ねる可能性があるためです。
したがって、XがY(Z)の代理人となり遺産分割協議をするときには、Z(Y)の特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
3、特別代理人の選任手続き
特別代理人を選任するためは、次のような手続きが必要になります。
-
(1)家庭裁判所への申し立て
特別代理人の選任手続きは、子どもの住所地の家庭裁判所に「特別代理人選任申立書」と必要書類を添付して申し立てることからはじまります。
必要な費用は、特別代理人の選任が必要な子ども一人につき800円(収入印紙で納付)と、連絡用の郵便切手代です。 -
(2)申立時の標準的な必要書類
遺産分割協議の特別代理人選任を申し立てるときに必要となる書類の例としては、主に次のようなものがあります。
- 利害関係人が申し立てるときには利害関係を証する戸籍謄本など
- 未成年者の戸籍謄本
- 親権者などの戸籍謄本
- 特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票
- 利益相反に関する資料(遺産分割協議書案)
戸籍謄本や住民票は、市区町村の窓口または郵送で請求して入手することができます。
なお「申立時に戸籍を入手することができない」などの事情により書類を揃えることができない場合には、申し立て後に追加で提出することも差し支えないとされています。
また、上記のほかに「審理に必要な書類がある」と裁判所が判断した場合には、追加書類の提出を求められることもあります。
いずれにしても、申し立ての前に申立先の家庭裁判所に相談・確認をしておくことで、より確実に手続きを進めることができるのです。 -
(3)選任審判書の送付
裁判所は、特別代理人候補者と未成年者との関係や利害関係の有無などを考慮したうえで、適格性を判断します。
裁判所が特別代理人の選任を認めたときには、「選任審判書」が申立人と特別代理人に送付されます。
なお、選任が認められなかったときでも、申立人が不服申し立てをすることは認められていません。
また、特別代理人は、審判書に記載された審判で決められた行為に限り、代理権を行使することができます。そのため、審判で決められた行為が終了した時点で、特別代理人の代理権も消滅するのです。
4、特別代理人の選任の注意点とは
遺産分割協議において特別代理人を選任する際には、以下の二点に注意する必要があります。
-
(1)申立時までに遺産分割の内容を決めておく
特別代理人の選任申し立てでは、「利益相反に関する資料(遺産分割協議書案)」の添付が必要になります。
基本的には、遺産分割協議書案の内容は、特別代理人の選任を申し立てた後に、そのまま遺産分割協議書の内容となります。
そのため、申し立てを行った段階で、その他の共同相続人の合意を得て協議をほぼ成立させておくことが必要となるのです。
「協議書“案”だから、不備があっても後から修正できるだろう」という考えは通じないので、注意してください。 -
(2)遺産分割協議書案の内容に注意
基本的に、は、未成年者にとって不利にならない内容(最低限法定相続分を取得する内容など)であるほうが、裁判所からの審判が得やすくなります。
ただし、相続財産の大部分が不動産であり、親権者が不動産を取得して活用し、幼い未成年者の養育費にあてるような事例では、遺産分割協議書案そのものの内容は未成年者に不利なものであったとしても、受理される可能性はあります。
ただし、このような事情があるときには、上申書を提出したり裁判所の照会などに対して適切に回答したりすることを通じて、「最終的には、未成年者に不利益は生じない」と裁判所を説得する必要があるのです。
5、まとめ
本コラムでは、「遺産分割における特別代理人」について役割や選任方法、注意点について解説いたしました。
基本的に、相続人のなかに親権者と利益が相反する未成年者がいる場合には、特別代理人の選任が必要となります。
特別代理人の選任を裁判所に認めてもらうためには、遺産分割協議書案の内容は未成年者に不利益をもたらさないものであることを裁判所に説得する必要があるのです。
しかし、遺産分割協議書案の内容をどのようなものにするべきかがわからず、お困りなられる方も多いでしょう。
ベリーベスト法律事務所では、グループに税理士や司法書士が在籍しているため、連携して対応も可能です。
「この遺産相続は未成年者との利益相反になるのか?」という些細な疑問から、特別代理人を選任する手続きの具体的な方法まで、ベリーベスト法律事務所 船橋オフィスにまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|