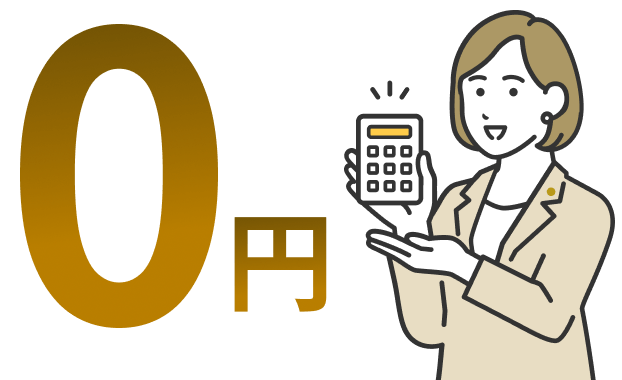遺言で子どもを認知するにはどうしたらいいのか? 手続きについて解説
- 遺産を残す方
- 遺言認知
- 広島

「家族には話していないが、認知をしていない隠し子がいる」、「家族には話しているが、認知はしていない」というような悩みをお持ちの方もいるのではないでしょうか。
そのような悩みをお持ちの方の中には、今は事情があって認知をしていなくても、「自分が死んだ後は認知をして相続財産を少しは渡したい」と、思っている方もいるかもしれません。
そこで、今回は、遺言認知の方法や認知された子どものメリットやデメリットについて解説していきます。
1、遺言認知とは
遺言認知とは、遺言によって子どもを認知することです。婚姻関係にある女性から生まれた子どもは父親が明確ですが、婚姻関係にない女性から生まれた子どもは、嫡出推定が及ばないため、父親が明らかではありません。そこで、父親であることを自ら申し出て、父子関係を設定することができます。この手続きを「認知」といいます。
認知がない子どもは、戸籍の父親欄が空欄で父親がいない状態です。養育費も払ってもらえず、父親の財産の相続権もありません。このような不都合をなくすのが認知です。
認知すると、その効力は出生のときまでさかのぼりますので、生まれたときから認知した父親の子どもとして扱われるようになります。なお、認知する子どもが成人している場合は本人の承諾が必要になります。また、胎児を認知する場合は母親の承諾が必要になります。
遺言認知が利用されるケースとしては、愛人との間の子どもの認知があります。生前は家族の手前、認知した場合にはトラブルになることから認知しないものの、亡くなった場合には、愛人との間の子どもにも相続財産を分け与えたいということで遺言認知するということがあります。
2、認知される子どものメリットとデメリット
-
(1)認知されることのメリット
認知されることで、子どもが受けるメリットとしては、子どもが未成年の場合、父親に扶養義務が発生し、養育費を請求することができます。また、相続権が認められるようになります。
母親が経済的に苦しい場合には、父親から養育費を受け取れるようになることは、大きなメリットといえます。相続権についても、嫡出子と同様の地位が認められています。かつては、民法上、婚外子の法定相続分は、嫡出子の2分の1と規定されていましたが、この規定は法の下の平等を定める憲法に違反するとして裁判となりました。
最高裁(平成25年9月4日大法廷判決)は、裁判官の全員一致で、民法の規定は、憲法14条1項に違反していたと判断しました。この判例によって、民法が改正され、婚外子(非嫡出子)の法定相続分は嫡出子と同等になりました。
その結果、たとえば、認知した父が死亡して、妻とその夫婦の子どもである嫡出子がひとり、婚外子(非嫡出子)ひとりという場合、相続分は、妻が2分の1、嫡出子が4分の1、婚外子が4分の1となります。 -
(2)認知されることのデメリット
認知されることのデメリットとしては、子どもが成人していて、父親が高齢などで生活が困窮している場合、子どもは親に対する扶養義務があるため、扶養しなければならなくなる可能性があることです。子どもが小さいうちは認知せず、養育費も支払わないで、自分の生活が厳しくなると、認知して扶養を求めるというのはあまりに身勝手です。そのため、法律上、成人になった子どもを認知する場合には、子どもの承諾が必要とされています。
ただ、子どもが19歳の場合、母親の承諾によって認知されてしまうので、母親が認知について承諾してしまうと、父親の扶養義務が発生してしまう可能性があります。これは子どもにとってデメリットといえます。 -
(3)相続分への影響
遺言がない場合のために、相続人の相続分は法律によって定められています。これを、「法定相続分」と呼びます。法定相続分は、相続人が「配偶者と子ども」の場合がそれぞれ2分の1になります。相続人が「配偶者と直系尊属」の場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。相続人が「配偶者と兄弟姉妹」の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
遺言認知によって婚外子を認知すると子どもの数が増えるので法定相続分が変わります。たとえば、配偶者と子どもがひとりという場合、法定相続分に従えば配偶者が2分の1、子どもが2分の1となりますが、これに婚外子ひとりが追加になると、子どもはふたりになるので、子どもの相続分がそれぞれ4分の1ずつとなります。遺言認知する場合には、遺言するのだから、認知だけでなく遺産の配分についてもしっかりと指定しておくことがトラブルを防ぐ上で大事になります。
また、相続税の計算においても認知によって計算が変わってきます。相続税の計算においては、基礎控除が認められますが、その額が変わります。
基礎控除の計算式は「3000万円+600万円×法定相続人の数」なので、法定相続人が認知によってひとり増えると基礎控除額も600万円増えることになります。
その他、死亡保険金が支払われる場合、「500万円×法定相続人の数」は非課税になるので、こちらも認知によって法定相続人の数がひとり増えると500万円増えることになります。 -
(4)戸籍の記載(婚外子の分)
嫡出子と非嫡出子(婚外子)の記載は次の通りです。
【嫡出子】
【名】A男
【生年月日】平成○年○月○日
【父】戸籍X男
【母】戸籍Y子
【続柄】長男
【非嫡出子】
【名】B男
【生年月日】平成○年○月○日
【父】
【母】法務Z子
【続柄】長男
これが認知されると、空欄だった「父」欄に認知者の氏名が記入されます。【名】B男
【生年月日】平成○年○月○日
【父】戸籍X男
【母】法務Z子
【続柄】長男
さらに身分事項欄に認知の内容が追加されます。【認知日】令和○年○月○日
【認知者の氏名】戸籍X男
【認知者の戸籍】○○県○○市○○町○丁目○番地 戸籍X男
これにより、戸籍を見れば認知された事実がわかります。
3、遺言認知の手続きの流れ
遺言認知の手続きの前提として、遺言についての理解が必要なので、遺言の種類とそれらの特徴について簡単に解説します。
-
(1)遺言の種類
遺言には、普通方式の遺言と特別方式の遺言があります。特別方式の遺言は、死亡危急者遺言と呼ばれるもので、遺言者が生命の危険が差し迫った状況にいる場合に認められる特別の遺言です。普通遺言より作成要件を緩和しているのが特徴です。
ただし、死亡危急者遺言は、遺言者に生命の危険が差し迫ったという特別な状況下で例外的に許される方式であるため、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになったときから6か月間生存するときは、その効力を生じないとされています。
普通方式の遺言には、
① 自筆証書遺言
② 公正証書遺言
③ 秘密証書遺言
があります。① 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、文字通り遺言する人が自ら、自筆で遺言を書くものです。署名だけでなく、日付や内容を全て自筆で書き押印する必要があります。代筆やパソコンなどで作成したものは無効になります。ただし、財産目録を添付する場合には、その目録については、自書でなくてもかまいません。この場合、遺言者は、その目録のすべてのページに署名し、印を押さなければなりません。
印鑑の種類については、法令上規定はされていませんが偽造等の防止の観点から、実印を使用する方が無難です。自筆証書遺言を修正する場合は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければならないことになっており、これが三文判であれば勝手に修正されるおそれがあるからです。
自筆証書遺言の特徴は、誰にも知られずに、ひとりで簡単に作れることです。ただ、素人が書いた場合、必要な要件を満たさず遺言が無効となってしまう場合があります。また、本人しか所在がわからないような場合、自室証書遺言が死後発見されないというリスクもあります。
遺言を発見した者は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して検認してもらう必要があります。なお、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立ち会いがなければ、開封することができないとなっています。
検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。あくまで形式的に確認するのみで、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
② 公正証書遺言
公正証書遺言とは、証人ふたりの立ち会いのもと、公証人が遺言者の口述に基づいて遺言書を作成し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させて、遺言者、証人、公証人が署名押印するものです。なお、口がきけない方や耳が聞こえない方も、手話通訳者や筆談を用いて公正証書遺言を作成することができます。
証人には、未成年者や推定相続人などの利害関係人はなれませんので、知人などに依頼する必要があります。
公正証書遺言の特徴は、公証人が遺言を作成するので、基本的に不備になることがなく、原本が公証役場で保管されるため、変造や紛失のおそれがないことです。そのため、検認手続きは不要です。ただ、作成には費用がかかります。
③ 秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言に署名押印し、遺言者がその証書を封じ、これを封印したものを、公証人役場に持ち込み、日付と遺言者名を封紙に記載した上で、証人2名以上と公証人がともにこれに署名・押印するものです。秘密証書遺言は、自筆でなくてもかまいません。パソコンで作成可能です。ただし、署名は自筆でする必要があります。
秘密証書遺言は、公正証書遺言と異なり、公証人役場では遺言書を保管せず、その保管は遺言者が行います。もちろん、貸金庫や弁護士に保管を依頼することはできます。秘密証書遺言のメリットは、遺言の内容を秘密にでき、偽造などを防げることです。ただ、公証人役場に支払う費用が発生する点と紛失のリスクがある点がデメリットです。検認の手続きが必要になりますので、家庭裁判所に検認を請求しなければなりません。 -
(2)遺言認知の手続き
子どもを認知する遺言書がある場合、遺言執行者は就任から10日以内に認知の届け出を市役所にしなければなりません。なお、認知する子どもが成人している場合は本人の承諾書が必要になります。また、認知する子どもが胎児の場合は母親の承諾書が必要です。遺言執行者がいない場合には、家庭裁判所に申し立て遺言執行者を選任してもらう必要があります。
4、遺言認知する際、留意すべきこと
遺言認知を行う場合、やはり家族への配慮が必要になります。婚外子の存在を知らせてなかった場合はもちろん、知らせていた場合であっても、認知をするとなると相続分に変化が生じるのでその配慮が求められます。
具体的には、遺言認知の場合、遺言を書くので遺産の分配についても正確に書いておくことが求められます。遺産の分配がはっきりしていないと相続人全員で遺産分割協議をしなければならず、嫡出子と非嫡出子が話し合いをしなければならなくなります。どちらにとっても気まずい状況だと思いますので、これを避けるためにも遺産の分配をはっきりさせておく必要があります。
また、遺言認知では、必ず遺言執行者が必要なので、遺言で遺言執行者を定めておくことが重要です。そうでないと相続人が家庭裁判所に申し立てる必要があるからです。遺言執行者として指定すべき人は、未成年者と破産者、成年被後見人など以外特に法律上制限はないので、信頼できる人や弁護士などを指定すると良いでしょう。
5、まとめ
今回は、遺言認知について解説してきましたが、「認知」というのは家族にとって非常にデリケートな問題です。認知される非嫡出子と被相続人の配偶者や嫡出子との間でトラブルにならないよう、財産の配分にも配慮することが重要です。
さまざまなご事情によって、遺言認知を検討されているようでしたら、まずはベリーベスト法律事務所 広島オフィスまでご相談ください。弁護士が適切なアドバイスを行いつつ、着実に手続きが進むようサポートいたします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています