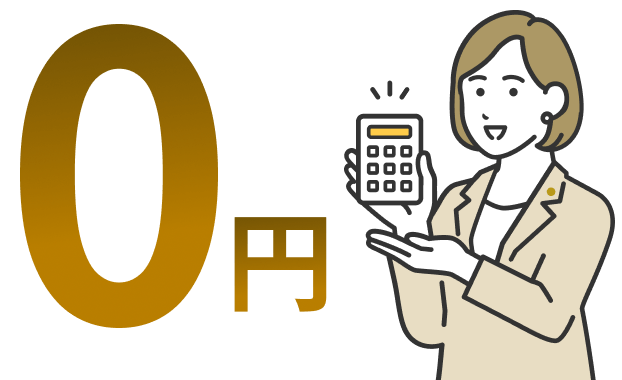相続発生後の養子縁組の解消は相続に影響するのか? 死後離縁について解説
- その他
- 死後離縁
- 相続

子どもを持つ人が再婚した場合、その人の子どもと再婚相手とは法律上は他人の関係であり、親子とはなりません。再婚相手と子どもとの関係を法律上の親子とするためには、養子縁組をする必要があります。
しかし、養子縁組をした後に、再婚相手が死亡した場合には、「親子関係を解消して、縁を切りたい」と希望する人がいます。また、再婚相手に実子がいる場合には、「相続トラブルに巻き込まれたくないとから、離縁したい」と希望されるケースもあるのです。
死んだ相手との養子縁組を解消するための手続きは、「死後離縁」と呼ばれます。本記事では、死後離縁の内容や相続に与える影響などについて、ベリーベスト法律事務所 広島オフィスの弁護士が解説いたします。
1、死後離縁とは
死後離縁とは、普通養子縁組をした親子のどちらか一方が亡くなった場合に、生存している者が親子関係を終了されるための手続きです。
死後離縁をおこなうためには、家庭裁判所にまで、許可の申し立てをする必要があります。家庭裁判所は、審判をしたうえで、許可を出すかどうかを判断します。
そして、家庭裁判所からの許可が出されたら、「縁組解消」の効果が発生して、離縁が成立することになるのです。
養子縁組の際に名字が変わっている人は、離縁した場合、原則として元の名字に戻ることになります。ただし、縁組期間が7年以上ある場合は、離縁の日から3か月以内に「離縁の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出することで、離縁の際に名乗っていた氏を続用することができます。
なお、「死後離縁」と似た手続きとして、「死後離婚」があります。
死後離婚とは、配偶者の死後に、義理の父母など配偶者の血縁者との関係を無くすための手続きです。配偶者が死亡すると婚姻関係も消滅しますが、死亡した配偶者の親族との関係が切れるわけではありません。
配偶者が亡くなった後も、配偶者の親族と付き合いを続けたい場合にはそのままでも構いませんが、死亡した配偶者の親族との関係は断ち切りたいという場合には、「姻族関係終了届」を市区町村役場に提出する必要があります。配偶者の死後におこなわれることから、この手続きが「死後離婚」と呼ばれているのです
「死後離婚」では、「死後離縁」と異なり、家庭裁判所から許可を得る必要はありません。単に市区町村役場に届出をするだけで効力が発生します。死後離婚は、死亡した配偶者の親族との関係を断ち切るだけの手続きなので、相続人である配偶者の地位に変更は生じません。したがって、相続には全く影響しないのです。
「死後離縁」は親と子の関係を断ち切る手続きであるのに対して、「死後離婚」は生存配偶者と死亡配偶者の親族との関係を断ち切る手続きである、という違いがあります。
死後離婚よりも死後離縁のほうが厳格な手続きが求められるのは、死後離婚は「姻族関係」が消滅するにすぎないのに対し、死後離縁では「直系血族関係」が消滅する、という違いがあるためです。
姻族の場合、特別の事情がない限り扶養義務は負いませんが、直系血族の場合には扶養義務があります。「死後離縁」により、直系血族関係が無くなれば扶養義務も無くなるという意味で大きな法律上の変動が生じるので、家庭裁判所の判断が求められることになるのです。
2、死後離縁が相続に与える影響
-
(1)死後離縁の効果
死後離縁をした場合の効果としては、養親との養子との関係が無くなることによって、養親の親族との関係も終了することになります。
しかし、死亡するまでは養子であったために、死後離縁したとしても相続に影響はありません。遺産分割が終了していない時点で、養子が死後離縁をしたとしても、相続権が失われるものではなく、養親の遺産はそのまま相続することになります。実子がいる場合であっても、実子と同様に相続を受けることができます。なお、実子との間で遺産分割でもめることを避けたいという場合には、相続放棄をすることができます。 -
(2)死後離縁しない場合の相続の範囲
死後離縁してもしなくても養子が養親の遺産について相続分があることは変わりませんが、死後離縁してない場合には養親の実子がその後亡くなり、配偶者や子がいなければ養子が兄弟姉妹として相続人になります。
また、養親の兄弟姉妹が亡くなり、配偶者や子どもがいない場合には、養親が兄弟姉妹として相続人となります。しかし、養親はすでに死亡しているので、その養子が代襲相続人になります。
このように、死後離縁をしないと養親の一定の親族が死亡した場合に相続権が発生することがあります。「遺産がもらえる可能性がある」と考えると死後離縁をしないほうがよいとも言えますが、見方を変えれば、「相続争いに巻き込まれる可能性がある」ということにもなるので、その点には注意が必要です。また、親族関係を継続することで扶養義務も存続することになるため、その点も考慮する必要があります。 -
(3)生前の離縁
死後ではなく、生前に養子縁組を解消する方法としては、「協議離縁」「調停離縁」「審判離縁」「裁判離縁」の四種類が存在します。
協議離縁とは、当事者の協議により離縁するものです。
調停離縁とは、協議離縁ができないときに家庭裁判所に調停の申し立てをして調停が成立することにより離縁をすることです。
審判離縁とは、調停が不成立になったときに、家庭裁判所の裁判官が職権で離緑することです。
裁判離縁とは調停などで離縁できない場合に裁判所の判決により離縁することです。
いずれにせよ、離縁が成立するとその段階で、親子関係は無くなります。親子関係が無くなるので、当然、相続権は発生しないことになるのです。
3、死後離縁=相続放棄ではないため注意が必要
死後離縁すると「相続放棄」になると思われている方は多いようです。しかし、上述した通り、死後離縁したとしても、養親の相続には何ら影響はありません。
相続したくないのであれば、別途「相続放棄」の手続きをしなければなりません。相続放棄とは、名前の通り、「相続する権利を放棄する」ための手続きです。放棄をした相続人は、はじめから相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄をするためには、家庭裁判所に相続放棄をする旨の申述をしなければなりません。申述をする家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。申述ができる期間は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。この申述期間を経過すると相続放棄をすることはできなくなります。ただし、調査に時間がかかるような場合には、例外的に延長してもらうことができます。
なお、一旦相続放棄をしてしまうと、原則としてそれを撤回することはできなくなるので注意が必要です。
相続放棄の手続きに必要となる標準的な書類は、下記の通りです。
- 申立書
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
4、相続や離縁は弁護士へ相談を
死後離縁をするのに必要となる標準的な書類は、下記の通りになります。
- 申立書
- 養親の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 養子の戸籍謄本(全部事項証明書)
なお、死亡している人の戸籍については、死亡の記載があるものが必要になります。申し立てをする場所は、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所に申し立てをすると、家庭裁判所で審判がなされ、許可審判ということになれば、離縁が認められます。
許可審判が確定したら、申立人の本籍地または住所地の市区町村役場に養子離縁の届出をしてください。市区町村役場への届出をする場合、「審判書謄本」と「確定証明書」の提出が求められますので、家庭裁判所に申請をして交付してもらう必要があります。
相続は、お金が絡む問題であるため、仲のいい兄弟や姉妹であっても、トラブルに発展する可能性があります。
実子と養子が相続人の場合には、法定相続分は全く同じですが、実子としては「血のつながっていない他人が、自分の親の遺産を受け取る」と否定的な心情で受け止める場合もあるでしょう。したがって、通常の相続よりもトラブルが発生しやすい事例と言えるのです。
そのような場合には、当事者同士が直接話し合いをするのではなく、第三者が介入したほうが、冷静に協議がすすみます。また、相続では法律や税などに関する複雑な制度や手続きが関係するため、専門家である弁護士や税理士に相談したほうがよいでしょう。
弁護士に依頼すれば、相続での話し合いはもちろん、死後離縁の手続きや相続放棄の手続きについても代行してもらうことができます。仕事をしている方なら、平日に時間を取ることが難しい場合もあります。また、裁判所や市区町村役場での手続きも慣れないと大変なものです。遺産相続では、弁護士をうまく活用して、面倒な手続きやトラブルをできるだけ回避することをおすすめします。
5、まとめ
本コラムでは、死後離縁について解説してきました。
「死後離縁」という言葉から、養親の死亡後は一切縁を切ることのように思われがちですが、死亡した時点で相続は開始するため、死後離縁は相続には影響しません。したがって、遺産の分割について他の相続人たちと協議をおこなう必要があるのです。
相続自体をしたくないのであれば、死後離縁とは別に、「相続放棄の」手続きを取る必要があります。
ベリーベスト法律事務所 広島オフィスでは、相続について経験豊富な弁護士が在籍しております。また、ベリーベストグループに、税理士も在籍しているため、必要に応じて連携も可能になっております。死後離縁や相続について相談したいという場合にはお気軽にご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています